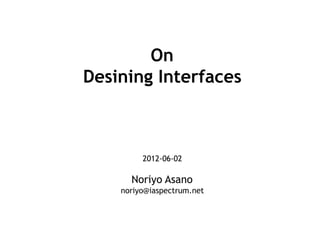
『デザイニング・インターフェース』読書会資料
- 1. On Desining Interfaces 2012-06-02 Noriyo Asano noriyo@iaspectrum.net
- 2. UX ?
- 3. 「ユーザーエクスペリエンス(UX)」という⾔言葉葉を 近頃よく⾒見見聞きするようになりました。 UXといわゆる普通の“体験”との違いとは何でしょうか。 それは、UXには利利⽤用する対象があるという点です。 つまりそこには、 何らかのツール/システム/テクノロジーが 必ず介在するのです。 たとえば… ⾳音楽を聴くという⾏行行為について考えてみましょう。
- 4. ⾳音楽を聴くという⾏行行為はもともと 「U」が付かない「X」、純粋な「体験」であると思います。 何か⾳音楽を聴きながら、 「私は今、その曲を利利⽤用している」 とか 「私は⾳音楽ユーザーである」 などと思うことは、あまりないですよね。
- 5. 昔々、すべての⾳音楽は「⽣生演奏されるもの」でした。 つまり、⾳音楽という形のないものを記録・再⽣生できる媒体 ー レコード盤、磁気テープ、CD、MD などなど ― が発明され、録⾳音技術というものが⽣生まれる前の時代のことです。 ⽣生演奏しかない時代には すべての⾳音楽体験は「X」であった。 しかし、録⾳音技術が⽣生まれたことにより そのテクノロジーを利利⽤用するという「UX」が ⾳音楽体験の中に含まれるようになった。
- 6. たとえば、今では⾳音楽を聴くという「X」の中に、 Amazonで掘り出し物のCDを⾒見見つける iTunesでせっせとプレイリストを作る ⾼高級ヘッドフォンで昔の⾳音源を聴き直す そういうさまざまな「UX」が関わっています。 その時、⾳音楽を体験する⾃自分は、 AmazonというWebサービスのユーザー iTunesというソフトウェアのユーザー ヘッドフォンというハードウェアのユーザー でもあるのです。
- 7. このように「UX」とは さまざまな技術の誕⽣生と進化の中で 「U」なしの、よりプリミティブな「X」の中に現れ、 時の流流れと共にその構成要素として不不可⽋欠となりつつあるもの。 私はそんな⾵風に捉えています。 さて、近頃では… こんな⾔言葉葉もいっぱい⽬目につきます。
- 8. UI/UX
- 9. UIとUX。 ユーザーインターフェースとユーザー体験。 その両者は決して無関係ではありませんが 同等な/並列列なものではありません。 UI/UXという⾔言葉葉を掲げていながら 実はそのどちらか⼀一⽅方の話をしているだけ。 そんな例例も少なくないように⾒見見えます。 今⽇日の読書会のテーマはUI設計です。 ですから、今⽇日はそれだけに集中したいと思います。 UX設計というまた別の次元の話は、またいずれとして。
- 10. ところで、 私たちは⽇日本語の「技術」ということばを ⼆二通りの意味で使うことがあります。 「○○社が開発した 技術(Technology)は凄いね」 「このツールを使いこなすにはそれなりの 技術(Technical ability)が要るね」
- 11. 技術を扱う私たちUI設計者は、常に Technology を意識識していますが Technical Ability の問題にはなかなか⼿手出しできません。 「技能」を向上させる啓発活動や教育といった領領域にまで UI設計者が踏み込むことは ⾮非常に難しいのが現実であるからです。
- 12. Technology でも、この両者が歩み寄ってこそ ユーザーインターフェースは その真価を発揮するのです。 Technical ability テクノロジーを追求するだけでなく ユーザーの技能を引き出すこと。 それが、UI設計者に求められるのではないでしょうか。
- 13. ユーザーの技能を理理解するために ⾏行行動経済学の「⼆二重プロセスモデル」を⾒見見てみましょう。 ⼈人間は何かを判断する時、実は2段階の処理理をしているという考え⽅方です。 問題 システム1 No (直感)による判断が 正しいか? システム2 Yes No (推論論)による判断が そのエラーを 正せるか? Yes 正解! 不不正解…
- 14. ユーザーの技能は、技術的なスキルだけでなく このような判断能⼒力力によっても⼤大きく左右されます。 操作のたびにいちいちシステム2の処理理を経由させられるUIは たとえスキルの⾼高いユーザーでも使いにくいものになってしまいます。 ユーザーの技能を⾼高めるには システム1のエラー発⽣生率率率をできるだけ抑えたい。 つまり、素早く反射的に、難しく考えずに操作できるような いわゆる“透明なインターフェース”を作ることが重要になります。 システム1(直感) システム2(推論論) 速い 遅い 並列列に処理理 順番に処理理 無意識識的・⾃自動的 管理理されている 努⼒力力は要らない 努⼒力力を要する 連想に基づく 規則に基づく
- 15. QWAN
- 16. そのようなUI設計を⾏行行う上で役⽴立立つのが 『デザイニング・インターフェース』で⽰示されている UIのデザインパターンです。 多くの⼈人にとっての使いやすさ・使い⼼心地のよさといったものには 何かしら根源的な共通の要素を⾒見見出すことができます。 建築家クリストファー・アレグザンダーはそれを 無名の質 / QWAN Quality Without A Name と名付けました。
- 17. Alive いきいきとした Eternal Comfortable ⼼心地よい 永遠の 無名の質 (QWAN) Egoless Whole 無我の 全⼀一的な Exact Free 正確な ⾃自由な 無名の質は本来ことばでは表せないものだが そこには7つの特性を⾒見見出すことができる。 それを実現し、かつ再現可能にするのが、パターン⾔言語である。 アレグザンダーは、そう考えました。
- 18. デザインパターンは、いわば単語のようなものです。 誰かとコミュニケーションする時に わずか⼀一つの単語で何かを伝えるのが難しいのと同じで、 個々のデザインパターンも単独で存⽴立立するものではありません。 単語が集まって⽂文章になるように どのパターンも互いに組み合わせてこそ その真価を発揮するのです。 あなたが作りたいUIを実現できそうなパターンを集め、 それらをうまく組み合わせて形にすること。 それは、あなた⾃自⾝身のパターン⾔言語を⽣生み出すということです。 そのような⼯工程を経て実体化されたUIには きっといくばくかの「無名の質」が備わっているはずです。
- 19. 「無名の質」を備えたUIは、 それ⾃自体が絶賛の的になることはないかもしれません。 でも、それでよいのではないでしょうか。 UIを操作すること⾃自体がUXの核⼼心である。 そんなケースは、ごく限られているはずです。 ある体験の中に何らかのUXが関わっているとして さらにそのUXの中で利利⽤用されるUIの役割とは、 本来の体験における⽬目的の達成を決して邪魔することなく いわば“⿊黒⼦子”のように助けること。 そんな⾵風に⾔言ってもよいかもしれません。
- 20. パターンを知り、活⽤用することは、 “ワンパターン”なUIをデザインすることとは違うのです。 さまざまなパターンを学ぶことで あなた⾃自⾝身のパターン⾔言語を作り上げる⼒力力を ⾝身につけること。 それが、デザインパターンの世界への扉を開く 『デザイニング・インターフェース』という本の意義であると 私は考えます。
- 21. I hope you enjoy designing.
