【D01】外国籍の子どもの保育について【青森中央短期大学/特別研究 松浦研究室】
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•45 views
"外国籍の乳幼児の保育環境について、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの外国籍等保育調査報告、総務省の住民基本台帳などの文献を通じて検討した。 この結果、就学前は生活や教育の実態が把握されていないケースが多く、これまでに各地で様々な具体的手立てが考案作成使用されているものの、その情報が共有されていないこと、そして園全体に理解の輪を広げることで保育の質を向上させられることが明らかとなった。"
Report
Share
Report
Share
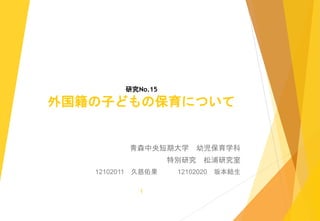
Recommended
Recommended
More Related Content
More from aomorisix
More from aomorisix (20)
【F19】伝統文化を伝承する地域のつながり構造~油川の地域ねぶた伝承の調査から~【青森公立大学/小田桐久夫】

【F19】伝統文化を伝承する地域のつながり構造~油川の地域ねぶた伝承の調査から~【青森公立大学/小田桐久夫】
【F14】青森大学生は参院選をどう見たか/10年後の青森は【青森大学/青森大学×NHK青森プロジェクト】

【F14】青森大学生は参院選をどう見たか/10年後の青森は【青森大学/青森大学×NHK青森プロジェクト】
【F13】青森ねぶた祭におけるIT活用の現状と可能性-他地域の祭りとの比較から-【青森大学/木村 琴美】

【F13】青森ねぶた祭におけるIT活用の現状と可能性-他地域の祭りとの比較から-【青森大学/木村 琴美】
【F12】ネット・SNSの普及やコロナ禍がもたらした地域社会の変化 -青森県の実例からの考察【青森大学/中田 昇】

【F12】ネット・SNSの普及やコロナ禍がもたらした地域社会の変化 -青森県の実例からの考察【青森大学/中田 昇】
【F04】最低賃金と有効求人倍率の関係【青森中央学院大学/工藤怜奈 古川莉子 浪岡晴夏(楠山ゼミ4)】

【F04】最低賃金と有効求人倍率の関係【青森中央学院大学/工藤怜奈 古川莉子 浪岡晴夏(楠山ゼミ4)】
【D01】外国籍の子どもの保育について【青森中央短期大学/特別研究 松浦研究室】
- 1. 研究No.15 外国籍の子どもの保育について 青森中央短期大学 幼児保育学科 特別研究 松浦研究室 12102011 久慈佑果 12102020 坂本結生 1
- 5. 外国籍の子ども 5 〇青森県にいる外国籍の子ども ・0歳~4歳の男の子の人数は27人、女の子は25人、5歳~ 9歳の男の子の人数は38人、女の子は26人 〈0歳~4歳の外国籍の子どもの人数が多い市町村BEST 3〉 第1位 弘前市(12人) 第2位 青森市(9人)、八戸市(9人) 第3位 三沢市(7人) 〈5歳~9歳の外国籍の子どもの人数が多い市区町村BEST 3〉 第1位 八戸市(15人) 第2位 三沢市(11人) 第3位 青森市(10人)、弘前市(10人)
